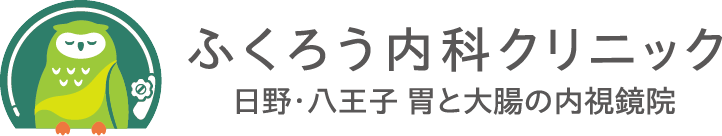日野市で健康診断を希望される方
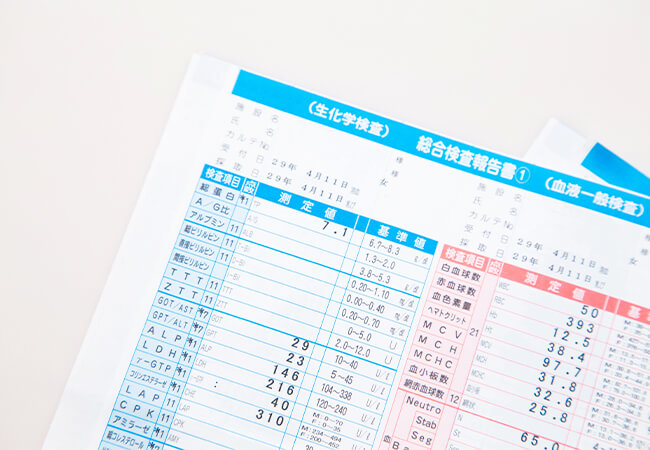
健康診断は、発症して間もなくは自覚症状が出にくく、気づいたときには重篤化しやすい生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症 等)などを早期に発見して、病状がどんどん進行する前に治療につなげるようにする、あるいは、自らの健康状態を把握し、できるだけ良好の状態に努めるといったことを目的に行われるものです。
この場合、法律で実施することが定められている健康診断と任意の健康診断に大きく分けられますが、法律で決められている健診には、代表的なものに特定健康診査(特定健診)があります。
これは生活習慣病を発症しやすいとされる40~74歳の世代を対象にしたもので、「高齢者の医療に関する法律」で定められているもので、1年に1回行うとされているものです(75歳以上の方は高齢者医療健康診査)。また40歳未満の方も職場や各自治体で健診が受けられるほか、学生であれば学校保健安全法に基づいた健康診断が実施されます。
当院では、特定健診、企業健診、日野市で行われるがん検診などを行っています。