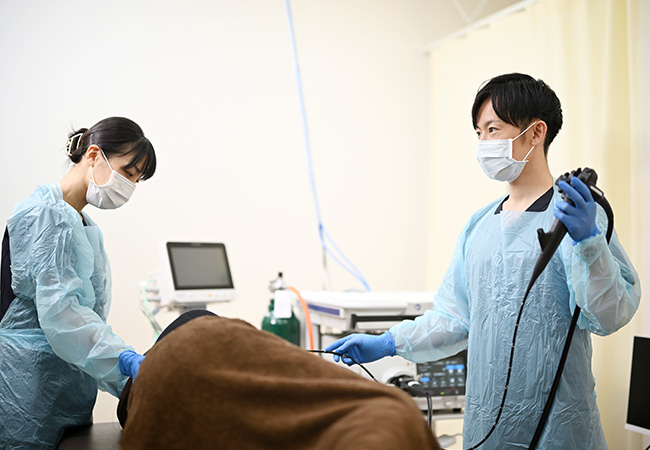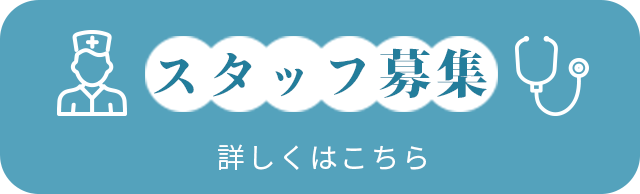ピロリ菌って何?

正式にはヘリコバクター・ピロリ( Helicobacter pylori )と呼ばれるらせん状の細菌で、胃粘膜に感染するバクテリアです。大きさは1~2μm程度で鞭毛と呼ばれるひげの部分を回転させて胃の中を移動します。
胃の中には、食べ物を消化し、食べ物の腐敗を防ぐために、胃液が胃粘膜から分泌されています。胃液には、強い酸が含まれているため通常の菌は生息できません。しかし、ピロリ菌はウレアーゼという酵素を作り出すことで、胃の中の尿素を分解してアンモニアを発生させます。
アンモニアはアルカリ性なので、ピロリ菌のまわりの胃酸が中和され生存可能な環境を作り出します。また、ピロリ菌はCagAという特殊なたんぱく質を胃粘膜内に分泌してがん化を進ませます。よって早期発見と治療により、胃がんを含むピロリ菌関連の疾患の予防と管理することが大切です。